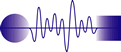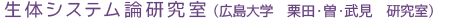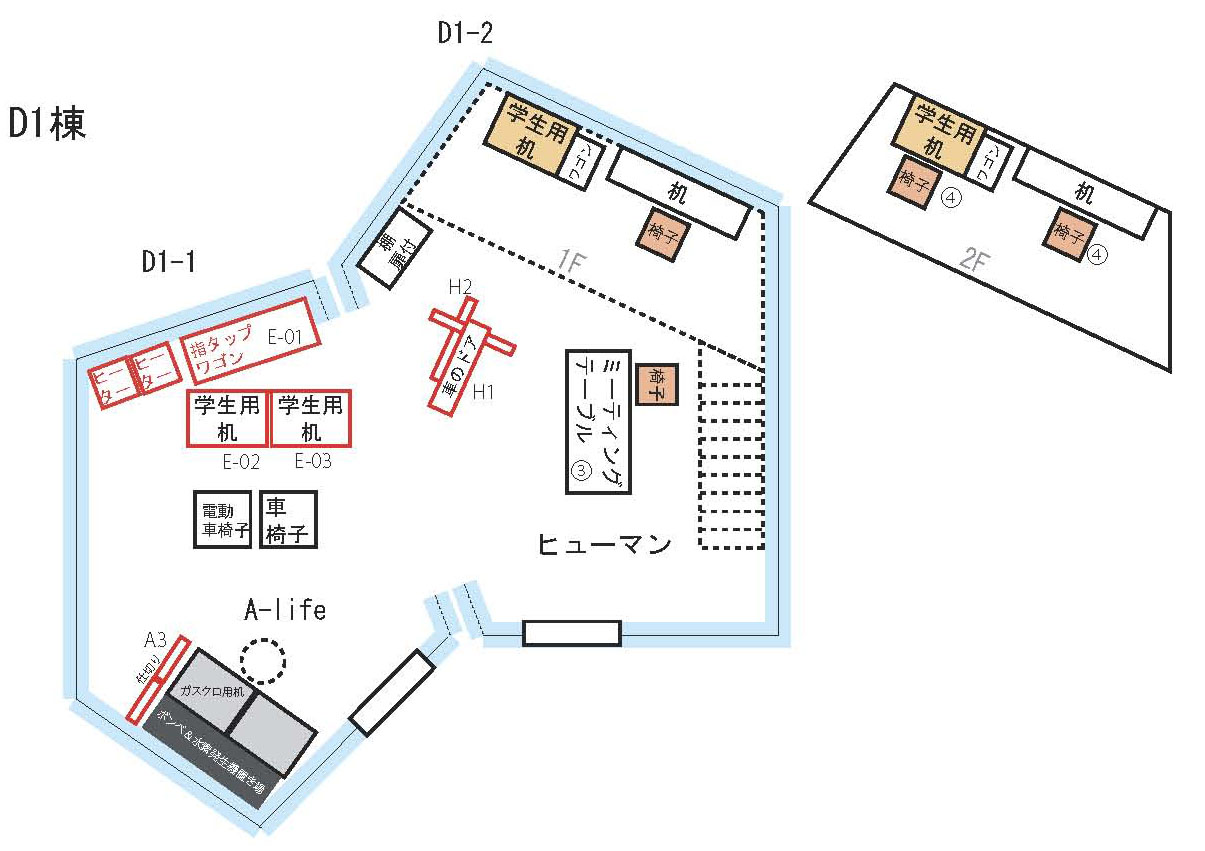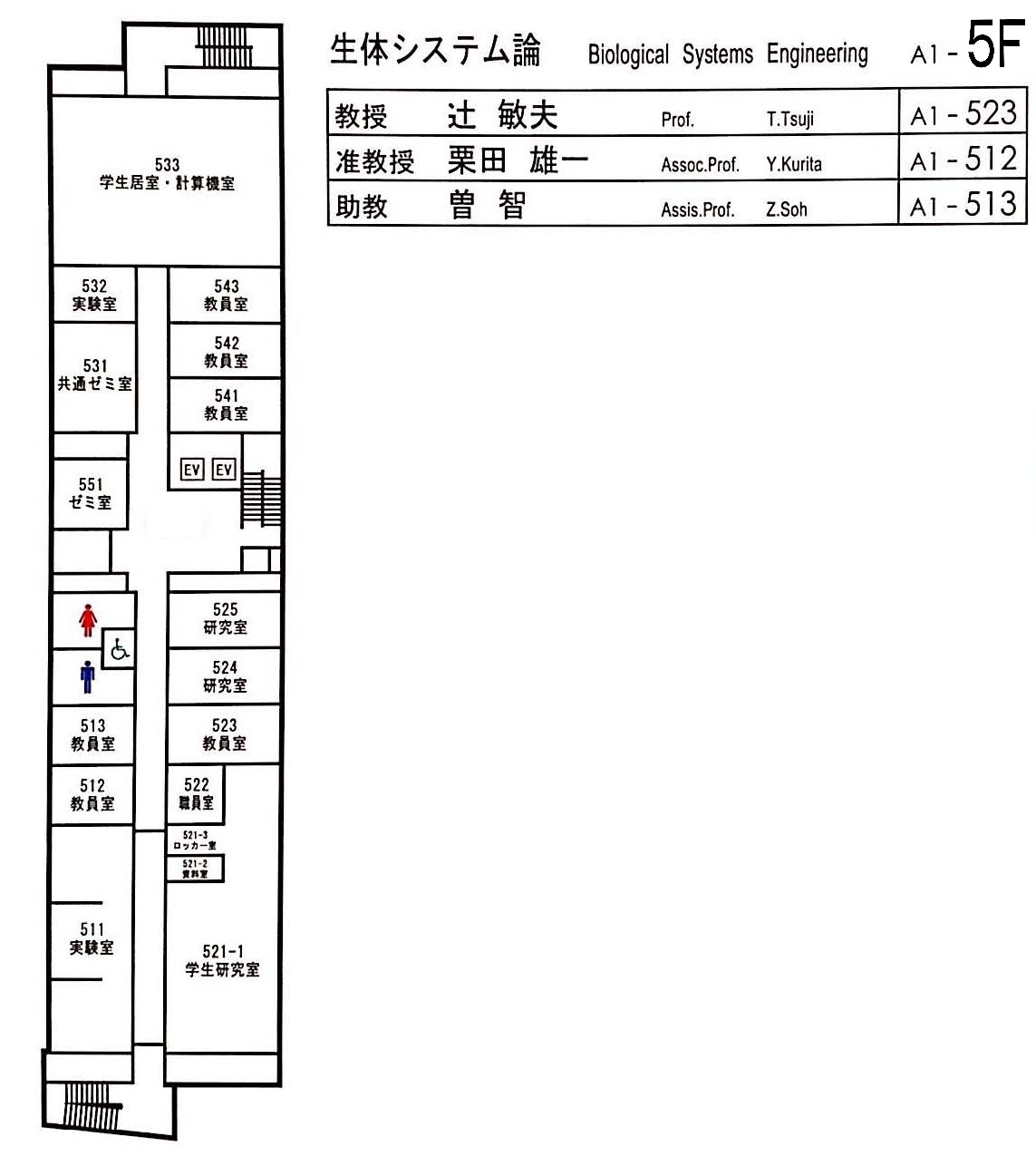2011年の年末から2012年の年始にかけて,IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2011),第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2011),日本機械学会第24回バイオエンジニアリング講演会という3つの学会に参加し,計7件の研究発表を行いました.
以前は12月中旬から1月中旬にかけての約1か月間に学会が開催されることなどほとんどなかったのですが,最近は年末年始も関係なくなってきています.
時代はますます加速度的にその変化のスピードを増していますね.
この変化に取り残されないようにするためには,研究のスピードとクオリティをできるだけ高く保つことが重要です.
今回の7件の発表はこの条件を十分にクリアしていたのではと思います.
以下は研究発表を行った研究室内の学生たちがまとめてくれた発表記録です.
2012年も質と量を両立した研究活動を続けていければと思います.
【2011 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2011)】
■開催地:Clock Tower Centennial Hall, Yoshida Campus, Kyoto University
■開催期間:December 20-22, 2011
■発表形式:口頭発表
■学会URL:http://www.si-sice.org/SII2011/
平松 侑樹
【論文情報】
A Novel Dual-arm Motion Discrimination Method Using Reccurent Probability Neural Networks for Automatic Gesture Recognition
Yuki Hiramatsu, Taro Shibanoki, Keisuke Shima and Toshio Tsuji
Proceedings of the 2011 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII 2011), pp. 1346-1351, Kyoto, Japan, December 20-22, 2011.
【質疑応答】
■Q1. 時間軸方向の正規化はどのようにしているのか.
−A1. 切り出した動作ごとにデータ数が30サンプルになるように間引きしています.
■Q2. 誰でも使えるシステムなのか.
−A2. はい.使用者ごとに動作の特徴をニューラルネットに学習することで,使用者に合わせたシステムを自動的に構築できます.
■Q3. 学習時間が大幅に減少できた一番の要因はなにか.
−A3. 各腕ごとの動作学習のみで双腕動作を識別できるためです.
これにより例えば各腕3動作の学習のみで15動作の識別が可能となるため,学習時間が低減できます.
■Q4. 弱い動作は切り出しできないのではないか.
−A4. 動作切り出しの閾値を適切に決定することで,加速度の小さな弱い動作も切り出し可能です.
【感想】
非常に落ち着いて発表できました.発表に合わせて頷いてくださる方々もおり,魅力的な発表ができたのではないかと思います.
しかし質疑応答の際に上手く答えることができず,島さんに補足して頂いた場面もありました.
反省点など多々ありますが,予稿作成から発表を通して非常に貴重な経験をさせて頂けたと思います.
今回学んだことを充分活かして修士論文に取り組んでいきたいと思います.
【第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2011)】
■開催地:京都大学 吉田キャンパス
■開催期間:2011年12月23〜25日
■学会URL:http://www.si-sice.org/si2011/
早志 英朗
【論文情報】
判別成分分析に基づく新しい次元圧縮型リカレント確率ニューラルネット
早志 英朗, 平松 侑樹, 芝軒 太郎, 島 圭介, 卜 楠, 栗田 雄一, 辻 敏夫
第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会論文集, pp. 559-562, 2011.
【質疑応答】
■Q1. 被験者の運動イメージを識別しているとのことですが,どうやってそのイメージをしてもらっているのでしょうか.
−A1. まずはじめに左右の人差し指を実際に動かしてもらい,次に先程の動作のイメージをしてもらうよう指示し計測しています.
■Q2. 被験者に正しいイメージをしてもらうためには,どのような方法をとるべきでしょうか.
−A2. 被験者の脳波の特徴の変化をバンドパスフィルタ等を用いてフィードバックする必要があると考えています.
■Q3. ネットワークへの入力信号は何チャネルでどれくらいの時間なのでしょうか.
−A3. 3chの脳波を計測し,それぞれを40Hzまでの10帯域にウェーブレットパケット展開を用いて分解し,計30帯域を20秒間入力しております.
【感想】
会場の雰囲気にのまれやや緊張してしまいましたが,発表,質疑応答ともおおむね問題なくできたと思います.
聞いていた方々の関心が脳波識別にあり,ネットワークの説明にあまり関心を持って頂けなかったようなので,もっとわかりやすい説明をする必要があると感じました.
他の研究室の発表も聞くことができ,初めての学会でしたが良い経験になりました.
佐々木 桂一
【論文情報】
筋骨格モデルを利用した上肢到達運動の効率性評価
佐々木 桂一, 栗田 雄一, 辻 敏夫
第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会論文集, pp. 1646-1649, 2011.
【質疑応答】
■Q1. 筋張力のグラフで不連続なのはなぜですか.
−A1. 筋力最適化計算で筋力が最小になる点を求めているために,不連続になる場合があります.
■Q2. 筋レベルでの運動効率評価は妥当なものか.
−A2. 現在はシミュレーション結果の妥当性は検証できていません.
今後,運動時の上肢の筋電位を計測することで,シミュレーションの妥当性を検証する必要があります.
【感想】
発表に関しては時間がかかってしまい,質疑応答の時間が短くなってしまったことは反省点です.
また質疑応答では,落ち着いて答えることができましたが,返答が不十分なものがあり,より研究内容を知る必要があると感じました.
今回の学会発表はとても良い経験となったので,今後の研究に生かしていきたいと思います.
丸元 崇弘
【論文情報】
非定常リズム信号を生成可能なCPGシナジーモデルの提案と指タップ運動機能評価への応用
丸元 崇弘, 植野 岳, 芝軒 太郎, 島 圭介, 栗田 雄一, 辻 敏夫, 神鳥 明彦, 佐古田 三郎
第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会論文集, pp. 1673-1676, 2011.
【質疑応答】
■Q1. 基本パターンはどのように導出しているのですか.
−A1. Bizziらが提案している筋シナジーの抽出方法を応用して導出しています.
この方法を用いることで基本パターン,重み係数,時間シフトの3つのパラメータを求めることができます.
基本パターンは乗法更新アルゴリズムという方法で行列を用いて求めます.
■Q2. 交差検定でCPG数を決定する具体的な方法を教えて下さい.
−A2. まず,計測されたリズム運動のデータをK分割します.1つをテストデータ,残りを学習データとして学習データからCPGを求めます.
そして,求めたCPGでテストデータをどのぐらい近似できるか近似精度として決定係数で算出します.
CPGの数を増やしていき,近似精度の変化が閾値より小さくなった場合,そのときのCPG数として決定します.
■Q3. システムを同定することの意義は何ですか.パラメータを求めて何がわかるのですか.
−A3. 提案するモデルを用いてシステム同定することで,どのパラメータが運動異常に影響を与えているかなど,運動異常の特性の違いを議論できればと考えています.
また,現在はシステム同定のみですが,同定したパラメータをモデル化して,さらなる議論を行っていきたいと考えています.
【感想】
発表は落ち着いてすることができました.
質問に対してはある程度納得してもらえるような答え方をすることができたと思います.
しかし,従来の定量評価システムとの違いをうまく伝えることができず,今後の目的をもう少し詳しく説明することができたと思いました.
また,準備と片づけを落ち着いてできなかったことが反省点です.
他の発表に関しては分野が違う内容でとても刺激になりました.
今後もこの経験を活かして研究を行っていきたいと思います.
宮本 健太郎
【論文情報】
小型魚類の水質汚染監視用バイオアッセイシステムの開発
宮本 健太郎, 来山 茂央, 曽 智, 平野 旭, 栗田 雄一, 辻 敏夫, 滝口 昇,大竹 久夫
第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会論文集, pp. 2389-2392, 2011.
【質疑応答】
■Q1. 一つの水槽に2匹の試験魚を入れて汚染判別を行わないんですか.
−A1. 行動解析の方は可能だと思いますが,信号計測が難しいと考え今回は1匹で汚染判別を行いました.
しかし,個体差の問題もあるので,今後そのようなシステムの構築を検討していきたいと思います.
■Q2. エタノールを投入せずに長時間計測した場合,warningやcautionと判別されないんですか.
−A2. 水質正常時が短時間では時々cautionと判別されますが,長時間の計測での汚染判別はまだ行っていないので今後行う予定です.
■Q3. このシステムでは化学物質の濃度の変化などは確認できるのですか.
−A3. 今回は試験魚の状態の変化から,水質が異常かどうかを判別するシステムなので濃度の変化は確認できません.
【感想】
発表に関してはある程度練習どおりできたと思います.
また,質疑応答から今後に向けての色々な課題が見えてきてとても有意義な学会でした.
今回の学会発表はとてもいい経験になったので,今後の発表に生かしていきたいと思います.
【日本機械学会第24回バイオエンジニアリング講演会】
■開催地:大阪大学豊中キャンパス 基礎工学部棟
■開催期間:2012年1月7日(土),8日(日)
■発表形式:口頭発表
■学会URL:http://www.jsme.or.jp/conference/bioconf12/index.html
大塚 紘之
【論文情報】
力覚重畳技術を利用した生体臓器の硬さ呈示
大塚 絋之, 栗田 雄一, 永田 和之, 服部 稔, 徳永 真和, 惠木 浩之, 辻 敏夫
日本機械学会[No.11-47] 第24回バイオエンジニアリング講演会講演論文集,7D13,2012.
【質疑応答】
■Q1.グラフに示している値は測定値か.
−A1.測定値を用いています.呈示目標は物体の力覚特性を,VR,ARでは装置の出力を測定しています.
■Q2.押し込み量などの位置情報はどうやって検出しているのか.
−A2.装置のみの呈示ではポテンショメータを使用し,鉗子を用いた呈示ではハプティックデバイスが検出した位置情報を使用しています.
■Q3.装置の出力は呈示している反力の何割なのか.
−A3.デバイスがあまり大きい出力ができないため,だいたい5割から6割ほどになります.
【感想・反省点】
発表はほぼ練習通り行うことができ,内容にも興味を持って頂けたようでした.
しかし,質疑応答で返答が不十分な場面があったため今一度自分の研究を整理し,適切な返答を行えるようにする必要がありました.
今回の経験を研究や発表に生かそうと思います.