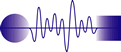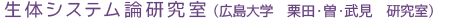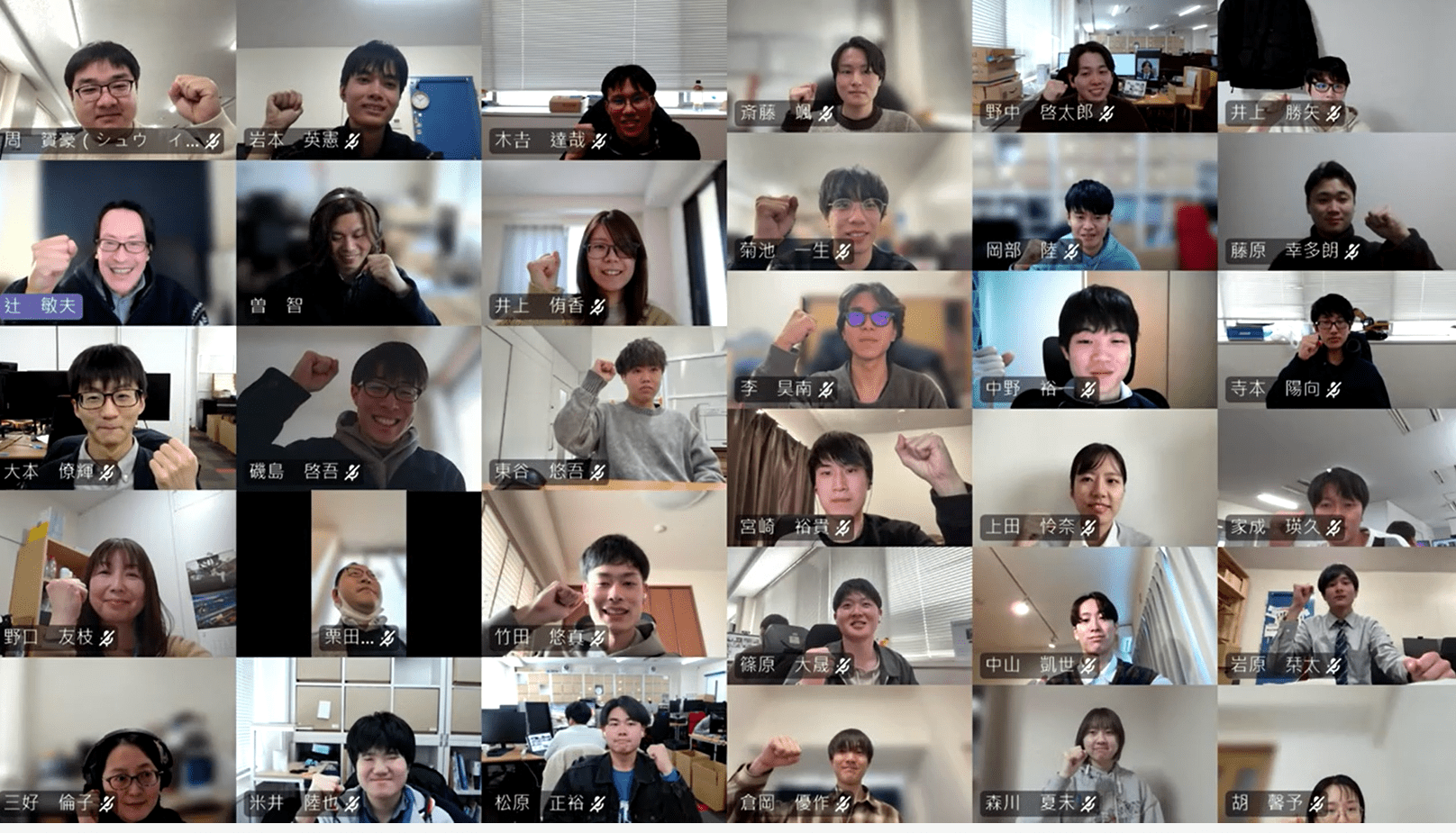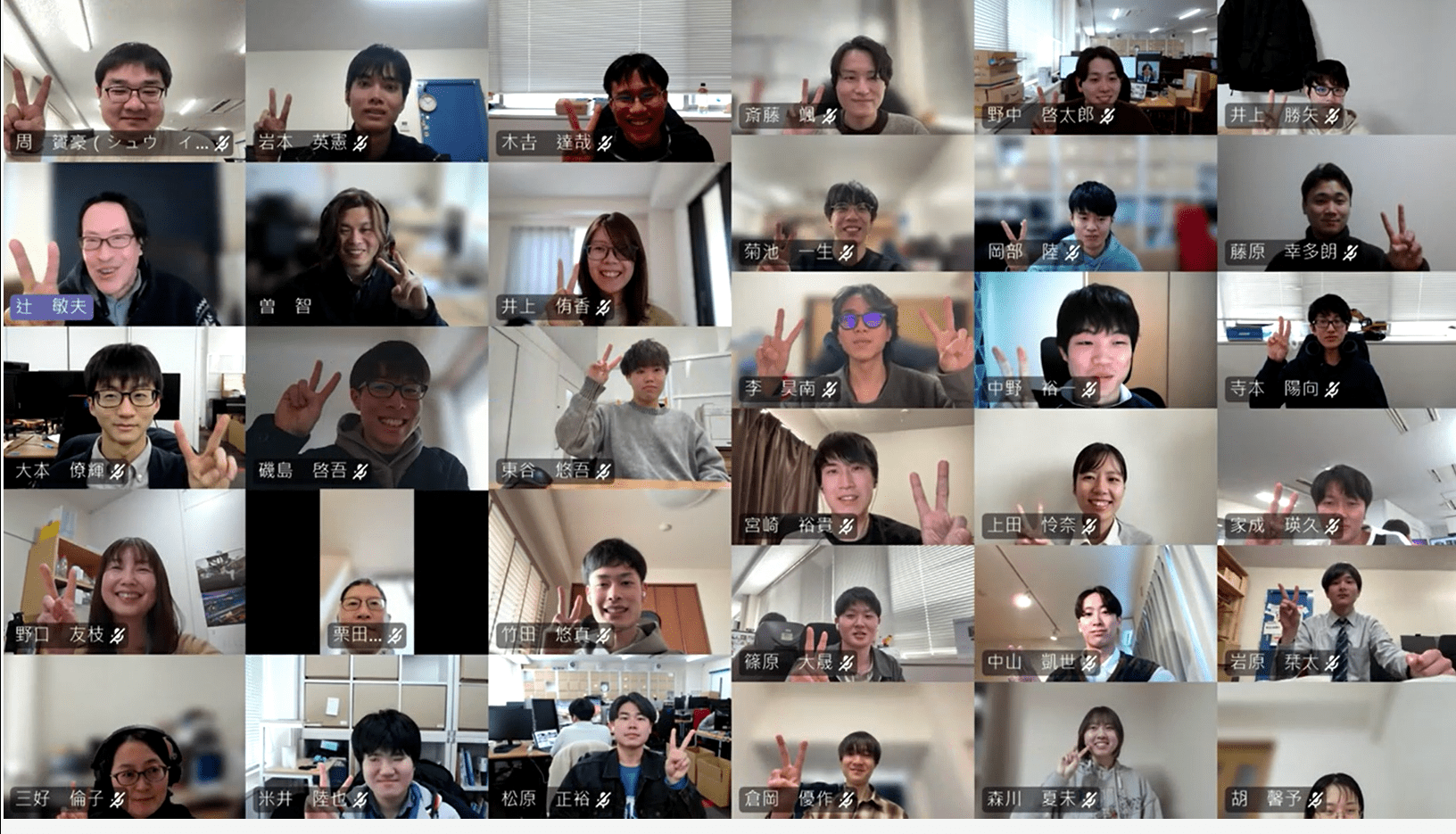■以下の国際会議論文が掲載されました.
Discriminative Analysis of Autistic Tendencies at 18 Months of Age Using Eye Gaze Characteristics in 4-, 10-, and 18-month-old Infants
Rena Ueda, Hirokazu Doi, Akira Furui, Koji Shimatani, Hideaki Hayashi, and Toshio Tsuji
2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2025), pp.265-270, Munich, January 21-24, 2025.
Non-Negative Tensor Factorization of Infant Spontaneous Movements: A Pilot Study for ASD Risk Evaluation of Newborn Infants
Rikuya Yonei, Akira Furui, Hirokazu Doi, Koji Shimatani, Hideaki Hayashi, Midori Yamamoto, Kenichi Sakurai, Chisato Mori, and Toshio Tsuji
2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2025), pp.275-280, Munich, January 21-24, 2025.
Design and Verification of Force Launch Patterns for Reducing Mental Load in Artificial Muscle Assist Devices
Iwamoto Hidenori, and Kurita Yuichi
2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2025), pp.141-146, Munich, January 21-24, 2025.
■国際会議The 2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration(SII2025)での米井君の発表がBest Student Paper Award Finalistを受賞しました.おめでとうございます!
Best Student Paper Award Finalist
2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2025), Munich
受賞者名: Rikuya Yonei
対象論文:Non-Negative Tensor Factorization of Infant Spontaneous Movements: A Pilot Study for ASD Risk Evaluation of Newborn Infants
Rikuya Yonei, Akira Furui, Hirokazu Doi, Koji Shimatani, Hideaki Hayashi, Midori Yamamoto, Kenichi Sakurai, Chisato Mori, and Toshio Tsuji
2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2025), pp.275-280, Munich, January 21-24, 2025.