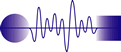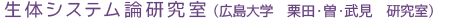近年,研究成果である学術論文の質の向上が強く求められており,研究論文を国際的に認められた論文誌で発表する必要性が高まっています.
具体的には,トムソン・ロイター(旧: Institute for Scientific Information (ISI))の引用文献データベースWeb of Scienceに収録される雑誌に掲載された論文(いわゆるSCI論文,日本語の論文は含まれない)が国際論文として評価される傾向にあり,
その中でもインパクトファクター (impact factor,IF) が高い雑誌に掲載された論文ほど高く評価される傾向があります.
・インパクトファクター(Impact Factor, IF)
インパクトファクターとは学術雑誌の影響度を評価する際に用いられる指標で,過去2年間においてその雑誌に掲載された各論文が次の年に平均して何回,引用されたかを示す尺度です.
ただし,対象とする学術雑誌や引用回数はWeb of Scienceに掲載されているSCI論文に限られます.分野が異なる学術雑誌を一概に比較することはできませんが,同じ分野であればインパクトファクターの高い雑誌ほど影響度が高いということになります.
本研究室において,2016年に掲載(あるいは掲載決定)になった論文のうち,SCI論文とそのインパクトファクターを以下に示します.
274. A novel blood viscosity estimation method based on pressure-flow characteristics of an oxygenator during cardiopulmonary bypass
Shigeyuki Okahara, Zu Soh, Satoshi Miyamoto, Hidenobu Takahashi, Hideshi Itoh, Shinya Takahashi, Taijiro Sueda and Toshio Tsuji
Artificial Organs (Thoughts & Progress) (Accepted)(SCI, IF=1.993).
275. Acute effect of oral sensation of sweetness on celiac artery blood flow and gastric myoelectrical activity in humans
Kohei Eguchi, Hideaki Kashima, Akiko Yokota, Kohei Miura, Masako Yamaoka (Endo), Harutoyo Hirano, Toshio Tsuji and Yoshiyuki Fukuba
Autonomic Neuroscience, Volume 197, pp. 41-45, May 2016 (SCI, IF=1.621).
276. Quantifying Parkinson’s disease finger-tapping severity by extracting and synthesizing finger motion properties
Yuko Sano, Akihiko Kandori, Keisuke Shima, Yuki Yamaguchi, Toshio Tsuji, Masafumi Noda, Fumiko Higashikawa, Masaru Yokoe and Saburo Sakoda
Medical & Biological Engineering & Computing, DOI:10.1007/s11517-016-1467-z, 54(6), pp.953-65. doi: 10.1007/s11517-016-1467-z., Epub 2016 Mar 31 (SCI, IF=1.797).
279. Surgical Grasping Forceps with Enhanced Sensorimotor Capability via the Stochastic Resonance Effect
Yuichi Kurita, Yamato Sueda, Takaaki Ishikawa, Minoru Hattori, Hiroyuki Sawada, Hiroyuki Egi, Hideki Ohdan, Jun Ueda, and Toshio Tsuji
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (Accepted) (SCI, IF=3.851).
280. Continuous Blood Viscosity Monitoring System for Cardiopulmonary Bypass Applications
Shigeyuki Okahara, Zu Soh, Satoshi Miyamoto, Hidenobu Takahashi, Shinya Takahashi, Taijiro Sueda and Toshio Tsuji
IEEE Transactions on Biomedical Engineering (Accepted) (SCI, IF=2.468).
281. Alteration of Arterial Mechanical Impedance Greater than that of Photoplethysmogram and Laser Doppler Flowmetry during Endoscopic Thoracic Sympathectomy
Elbegzaya Sukhdorj, Ryuji Nakamura, Noboro Saeki, Kensuke Yanabe, Abdugheni Kutluk, Hiroki Hirano, Harutoyo Hirano, Toshio Tsuji, and Masashi Kawamoto
Journal of Medical and Biological Engineering (Accepted) (SCI, IF=1.018).
282. A Mathematical Model of the Olfactory Bulb for the Selective Adaptation Mechanism in the Rodent Olfactory System
Zu Soh, Shinya Nishikawa, Yuichi Kurita, Noboru Takiguchi, and Toshio Tsuji
PLOS ONE (Accepted) (SCI, IF=3.54).
283. Endothelial Function Assessed by Automatic Measurement of Enclosed Zone Flow-mediated Vasodilation Using an Oscillometric Method Is an Independent Predictor of Cardiovascular Events
Haruka Morimoto, Masato Kajikawa, Nozomu Oda, Naomi Idei, Harutoyo Hirano, Eisuke Hida, Tatsuya Maruhashi, Yumiko Iwamoto, Shinji Kishimoto, Shogo Matsui,
Yoshiki Aibara, Takayuki Hidaka, Yasuki Kihara, Kazuaki Chayama, Chikara Goto, Kensuke Noma, Ayumu Nakashima, Teiji Ukawa, Toshio Tsuji, and Yukihito Higashi
Journal of the American Heart Association (JAHA) (Accepted) (SCI, IF=5.117).
一般に,IF=1以上はある程度読まれている雑誌,IF=3以上はかなり読まれている雑誌,IF=5以上は影響力の大きい雑誌と言われているようです.
今後も,SCI論文として掲載されるような質の高い研究論文をできるだけ多く発表できればと思っています.