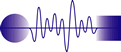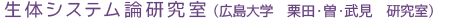第158回 広島大学オープンキャンパスに参加します.
2008.06.028月7日(木),8日(金)に東広島キャンパスで開催される平成20年度広島大学オープンキャンパスに参加することが決定しました.
広島大学オープンキャンパスは,毎年,8月初旬に開催されており,高校生や研究室外の大学生に対して,キャンパス内の施設や各部局,研究室の様子などを紹介し,普段は接することができないナマの情報を提供しようというものです.
本研究室では,4つの研究グループごとにデモンストレーションを用意し,本研究室で栗組んでいる研究内容をできるだけわかりやすく紹介できればと考えています.
最近,研究のアウトリーチ活動の重要性がよく指摘されています.
アウトリーチ活動という言葉は,研究成果を一般の人々に分かりやすく伝えるという意味で,近年,よく使われるようになりました.
もちろん,研究内容が充実していないのにアウトリーチ活動ばかりしていても意味がありませんが,自分達の研究内容や問題意識を専門家以外の人に伝えることは,広報活動としてだけでなく,自分達にとっても非常に重要なのではと思います.
他人に,特に専門知識を有していない人に自分の研究内容のおもしろさをうまく伝えることは,簡単なようでいて意外に難しいことです.
うまく説明を行なうためには,自分自身がその研究内容のポイントをきちんと理解しているかどうか,内容をわかりやすい言葉で表現するためのコミュニケーション能力を備えているかどうかが問われます.
普段から研究の意義やポイント,方向性などをよく考え,その内容を積極的に表現し,他人に伝えようとしている人は,きっと適切な説明ができるのだと思います.
非常によい機会だと思いますので,できるだけ積極的にデモンストレーションに参加し,自分の研究のおもしろさを自分の言葉で表現してみてください.
うまく説明ができれば,オープンキャンパスに参加してくれた人たちはきっと頷いてくださると思いますし,内容を理解してもらうことができれば,さまざまなコメントや新たな研究のヒントなどをいただけるかもしれません.
もちろん,オープンキャンパスに参加してくれた人たちが,将来,研究室に来てくれると非常にうれしいですしね.
8月7日(木),8日(金)は,両日とも13:30-16:00の間,研究室を公開します.
高校生だけでなく,本研究室の活動に興味を持ってくださっている方々の参加を歓迎します.
研究内容に関する質問やデモの感想など,いろいろなご意見がいただけれるとうれしいです.
どうぞよろしくお願いします.